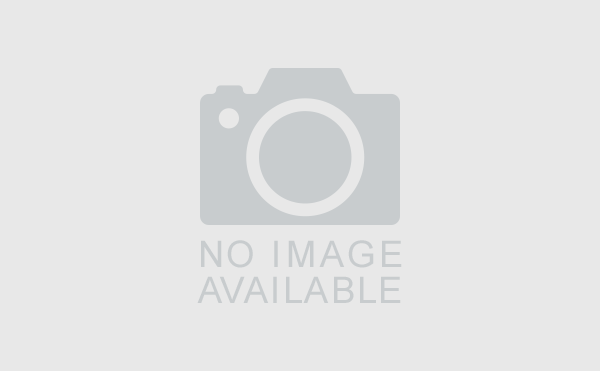巡回指導において、各種規程類をチェックいたしますが、特に運行管理規程については様々なものがあり、以下のような事例も見受けられました。
①そもそも貸切バス事業ではない内容の運行管理規程になっているケース
一般乗用 (タクシー)のものだと、規程の中で「(タクシー)メーター」という言葉が出てきたりします。一般貨物(トラック)のものだと、規程中に出てくる法律が「貨物自動車運送事業法」や「貨物自動車運送事業輸送安全規則」となっているので、明らかに業態が違うものと分かります。 もっともこのような状況だと運行管理規程が制定されていないとほぼ同義に近いかもしれません。まずもって業態が正しいものかどうか確認をし直してください。
②点呼時におけるアルコール検知器の使用の文言が入っていないケース
平成23年5月1日 から義務付けが始まっており、10年以上経過しておりますが未だに古いままになっていたことがありました。
③点呼時における睡眠不足の確認の文言が入っていないケース
平成30年6月から義務付けされており、当時の運行管理者等一般講習においても運行管理規程に睡眠不足の状況を確認する旨の文言を入れるよう案内をしておりました。
関連して、点呼の際に睡眠不足の確認を行う旨の文言は入っていますが、運行管理者の職務権限の方において睡眠不足の確認を行う権限を付与していない、というケースもありました。運行管理者に権限がなければ点呼時に確認が出来ないこととなるので、両方の条文において文言があるか確認してください。
ただ 、旅客自動車運送事業運輸規則第21条第5項における「睡眠不足」の記載については、従前の解釈運用通達において『「その他の理由」とは~』に含まれていたものを、改正後の運輸規則において明記するよう措置したものであるとされております。そのため、それらにあわせた記載をすることが望ましいところでありますが、 運行管理規程における表記等についてまでは厳格に定められていないため、事業者において法令の趣旨等を理解して表記している場合、それを否定することはできないものと思慮されるので、 睡眠不足の確認に関する記載がないからといって、即座に記載を行わなければいけない、ということまでにはならないようです。
この点については明記すべきという意見もあることから関東運輸局に確認を行ったことがあるのですが、
「基本的には明記するよう案内していただく内容にはなるが、明記していなくても事業者から適切に説明された場合には違反とまでは言えない。」
という回答をいただいたことがあります。
④運行指示書と異なる運行を行う場合の手続き
旅客自動車運送事業運輸規則第48条第1項において、運行管理者の業務が規定されていますが、その中の第12号の2において、運行指示書の作成・指示に関する内容があります。この条文もとに運行管理規程が作られているものも多いのですが、解釈運用通達第28条の2(1)に記載されている、「運行指示書と異なる運行を行う場合の手続き」について適切に把握されていないケースが多いです。この運行変更指示に関する定めを運行管理規程に盛り込むようにしてください。
これらの状況を踏まえ、最新の運行管理規程のサンプルを用意いたしました。
全部で4種類掲載しております。いずれも令和6年4月からの新制度に合わせた内容になっています。
また、令和7年4月30日付で告示化された業務前自動点呼の実施についても盛り込んだものを用意しました。
自社に合うものをお選びいただき、内容についても必要に応じて修正し、お使いください。
(特に点呼実施時間については、出庫の何分前に点呼を実施するのか空欄にしてありますので、自社の取扱いを明記する必要があります。
なお、遠隔点呼と自動点呼を両方とも実施している事業者につきましては、遠隔点呼対応版と自動点呼対応版、それぞれの規定を合わせていただくことでカバー可能です。
その際、第○条という部分をすべて訂正する必要はなく、例えば遠隔点呼対応版をベースに、「第20条の2」として業務前の自動点呼の条文を挿入したり、「第20条の3」として業務後の自動点呼の条文を挿入していただくことで、それ以降の条文を直す必要はなく使える形となります。もちろん業務後のみ自動点呼を実施する場合には、「第20条の2」として業務後の自動点呼の条文を挿入していただく形をとることができます。
組み合わせが多岐に渡るため、自社に合う形での編集を必ず行うようにしてください。
以下のファイルはいずれも編集可能なWordファイルとなっております。
運行管理規程例(令和6年4月1日改正対応基本版)
運行管理規程例(遠隔点呼対応版)
運行管理規程例(業務後自動点呼対応版)
運行管理規程例(業務前・後自動点呼対応版)