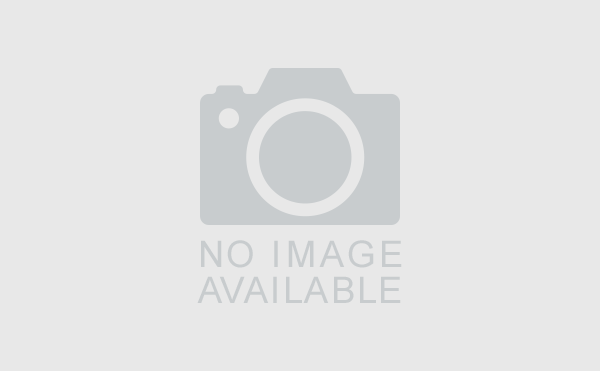営業所に選任されている運行管理者は定期的に講習を受講する必要があります。
まずは講習受講に関する制度を定めている法令を確認していきましょう。
道路運送法 第23条
一般旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行わせるため、国土交通省令で定める営業所ごとに、運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、運行管理者を選任しなければならない。
2 前項の運行管理者の業務の範囲及び運行管理者の選任に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
3 一般旅客自動車運送事業者は、第1項の規定により運行管理者を選任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを解任したときも同様とする。
旅客自動車運送事業運輸規則 第48条の4
旅客自動車運送事業者は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、次に掲げる運行管理者に国土交通大臣が告示で定める講習であって次項において準用する第41条の2及び第41条の3の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを受けさせなければならない。
一 死者若しくは重傷者(自動車損害賠償保障法施行令第5条第2号又は第3号に掲げる傷害を受けた者をいう。)が生じた事故を引き起こした事業用自動車の運行を管理する営業所又は法第40条(法第43条第5項において準用する場合を含む。)の規定による処分(輸送の安全に係るものに限る。)の原因となった違反行為が行われた営業所において選任している者
二 運行管理者として新たに選任した者
三 最後に国土交通大臣が認定する講習を受講した日の属する年度の翌年度の末日を経過した者
解釈運用通達 第48条の4
(1)講習は、「旅客自動車運送事業運輸規則第47条の9第3項、第48条の4第1項、第48条の5第1項及び第48条の12第2項の運行の管理に関する講習の種類等を定める告示」(平成24年国土交通省告示第454号。以下「講習告示」という。)に従い、選任届出をした日若しくは事故又は行政処分を受けた日において、当該年度に予定されていた講習が全て終了している場合等のやむを得ない理由がある場合を除き、講習告示に規定する時期までに受講させるよう指導すること。
(2)新たに選任した運行管理者とは、当該事業者において初めて選任された者のことをいい、当該事業者において過去に運行管理者として選任されていた者や他の営業所で選任されていた者は、新たに選任した運行管理者に該当しない。ただし他の事業者において運行管理者として選任されていた者であっても当該事業者において運行管理者として選任されたことがなければ新たに選任した運行管理者とする。
(3)特別講習の受講対象者については、以下に定めるところにより把握をし、講習告示に定めるところにより、受講対象者を指定し、速やかに講習の通知を行うこと。
また、特別講習の対象となった運行管理者又は統括運行管理者が当該事業者の当該営業所以外の営業所の運行管理者又は統括運行管理者に選任された場合であっても、講習を行うこと。
① 死者又は重傷者を生じた事故を惹起した営業所については、事故報告規則に基づく当該事故の報告の際に、同規則別記様式の運行管理者の欄に当該運転者の点呼又は指導監督を行った運行管理者など同様式の(注)(25)による運行管理者及び(注)(26)による統括運行管理者(選任されている場合に限る。)の氏名を当該事業者に記載させ、特別講習の対象となる運行管理者を把握し、その旨を記録し、保存すること。なお、道路交通法第108条の34の規定に基づいて死者又は重傷者を生じた事故で事業用自動車の運転者が第一当事者となったものとして通知があった事故のうち死者又は重傷者を生じたものについては、当該事故の報告を確実に行わせるよう指導すること。
② 法の規定のうち輸送の安全確保に係るものに違反をして行政処分を受ける営業所については、当該行政処分に先立つ監査において判明した、規則第48条各号の規定に対する違反について、相当の責任を有していると認められる当該営業所の運行管理者及び統括運行管理者(選任されている場合に限る。)を指定し、行政処分の命令書を交付する際に受講の指示を確実に行うとともに、その旨を記録し、保存すること。
(4)特別講習の趣旨は、死者又は重傷者を生じた事故を惹起した営業所の運行管理者又は法の規定のうち輸送の安全確保に係るものに違反をして行政処分を受けた営業所の運行管理者のうち当該事故又は当該行政処分について最も責任がある運行管理者を特定し、当該運行管理者に制裁を課すことではなく、当該営業所の統括運行管理者及び当該事故又は当該行政処分について相当の責任を有していると認められる運行管理者に当該営業所の運行管理者を代表して講習を受けさせ、当該営業所における運行管理の水準の向上を図り、一層の安全を確保することにあることから、事業者に対し、その旨を徹底すること。
(5)特別講習の通知を行う場合には、別添の「通知文の例」を参考とされたい。また特別講習の受講対象者だけでなく、当該営業所に所属する運行管理者に対して、2年度毎に受講させる基礎講習又は一般講習について、2年度連続で受講させなければならないことについてもあわせて周知されたい。
(6)運行管理者の講習の受講履歴については、保安担当が、監査担当と連携をとって講習実施機関に対し、定期的に講習実績の報告を求めるなど講習の受講状況の把握に努めること。
実際の講習受講に関する細かいルールについては、解釈運用通達に出てくる「講習告示」によるものとされます。
ではその講習告示(正式名称がものすごく長いのですが、一般的には講習告示で通用します)を確認してみましょう。
旅客自動車運送事業運輸規則第47条の9第3項、第48条の4第1項、第48条の5第1項及び第48条の12第2項の運行の管理に関する講習の種類等を定める告示
(用語)
第1条 この告示において使用する用語は、旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」という)において使用する用語の例による。
(講習の種類)
第2条 運輸規則第47条の9第3項、第48条の4第1項、第48条の5第1項又は第48条の12第2項の運行の管理に関する講習の種類は、次のとおりとする。
1 基礎講習(運行管理を行うために必要な法令、業務等に関する基礎的な知識の習得を目的とする講習をいう。以下同じ。)
2 一般講習(運行管理を行うために必要な法令、業務等に関する最新の知識の修得を目的とする講習をいい、同令第48条の4第1項又は第48条の5第1項の規定により国土交通大臣が認定する場合に限る。以下同じ。)
3 特別講習(自動車事故又は輸送の安全に係る法令違反の再発防止を目的とした講習をいい、同令第48条の4第1項の規定により国土交通大臣が認定する場合に限る。以下同じ。)
(運行管理者に受けさせなければならない運行の管理に関する講習)
第3条 運輸規則第48条の4第1項の規定により受けさせなければならない運行の管理に関する講習については、次条及び第5条に定めるところによる。
(基礎講習及び一般講習)
第4条 旅客自動車運送事業者は、新たに選任した運行管理者に、選任届出をした日の属する年度(やむを得ない理由がある場合にあっては、当該年度の翌年度)に基礎講習又は一般講習(基礎講習を受講していない当該運行管理者にあっては、基礎講習)を受講させなければならない。
2 旅客自動車運送事業者は、次に掲げる場合には、当該事故又は当該処分(当該事故に起因する処分を除く。以下「事故等」という。)に係る営業所に属する運行管理者に、事故等があった日の属する年度及び翌年度(やむを得ない理由がある場合にあっては、当該年度の翌年度及び翌々年度、前項、この項又は次項の規定により既に当該年度に基礎講習又は一般講習を受講させた場合にあっては翌年度)に基礎講習又は一般講習を受講させなければならない。
一 死者又は重傷者(自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)第5条第2号又は第3号に掲げる傷害を受けた者をいう。)を生じた事故を引き起こした場合
二 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第40条(法第43条第5項において準用する場合を含む。)の規定による処分(輸送の安全に係るものに限る。)の原因となった違反行為をした場合
3 旅客自動車運送事業者は、運行管理者に、第1項又は前項の規定により最後に基礎講習又は一般講習を受講させた日の属する年度の翌々年度以後2年ごとに基礎講習又は一般講習を受講させなければならない。
(特別講習)
第5条 旅客自動車運送事業者は、前条第2項各号に掲げる場合には、事故等に係る営業所に属する運行管理者(当該営業所に複数の運行管理者が選任されている場合にあっては、統括運行管理者及び事故等について相当の責任を有する者として運輸監理部長又は運輸支局長が指定した運行管理者)に、事故等があった日(運輸監理部長又は運輸支局長の指定を受けた運行管理者にあっては、当該指定の日)から1年(やむを得ない理由がある場合にあっては、1年6月)以内においてできる限り速やかに特別講習を受講させなければならない。
(5回以上受講する運行の管理に関する講習)
第6条 運輸規則第48条の5第1項の規定により運行の管理に関する講習を5回以上受講する者は、少なくとも1回、基礎講習を受講しなければならない。
講習告示を印刷されたい方がいらっしゃいましたら、こちらからダウンロードできます(PDFファイル)
これらの内容を踏まえ、整理をすると以下のようになります。なお、全体に共通しますが、受講すべき講習の種類は「旅客」事業者向けの講習である必要があります。貨物事業者向けの講習を受講した場合は無効となりますので注意してください。
○旅客自動車運送事業運輸規則 第48条の4に講習受講規定
・講習受講対象者(詳細は後述)
(1)①死者もしくは重傷者が生じた事故を引き起こした営業所の運行管理者
②行政処分を受けた営業所の運行管理者
(2)新たに選任された運行管理者
(3)前年度に講習を受講していない運行管理者
○講習告示において講習の種類や受講対象者を明記
・講習告示=旅客自動車運送事業運輸規則第47条の9第3項、第48条の4第1項、第48条の5第1項及び第48条の12第2項の運行の管理に関する講習の種類等を定める告示
・告示第4条第1項
新たに選任された運行管理者は、選任された年度に基礎講習か一般講習(過去に基礎を受けていない場合、最初に受けるのは基礎講習)を受講しなければなりません。
→新たに選任された、の定義
当該事業者(≒法人)において、今まで一度も運行管理者に選任されていなかったことを意味します(解釈運用通達第48条の4(2))。したがって、営業所間の異動の場合には対象にならないが、グループ会社間での異動の場合、異動先の事業者で選任されたことがなかった場合には、新たに選任された管理者に該当します。
→基礎講習を受講しなければならないケース
運行管理者試験を、「運行の管理に関する1年の実務経験」(正確には、「運行管理者試験日の前日において、自動車運送事業(貨物軽自動車運送事業を除く。)の用に供する事業用自動車又は特定第二種貨物利用運送事業者の事業用自動車(緑色のナンバーの車)の運行の管理に関し、1年以上の実務の経験を有する者」という表現になります)で受験し、運行管理者資格を取得した場合、運行管理者に選任されて最初に受講すべき講習は基礎講習でなければなりません。一般講習を受講しただけでは未受講扱いとなります。選任されている運行管理者が基礎講習を1回も受けていないということがないようにするための措置です。
・告示第4条第3項(※先に第3項を説明しています)
前年度に講習を受講していない管理者は、当該年度に基礎講習か一般講習を受講しなければなりません。これがいわゆる「2年(正確には年度)に1回受講する」ということの主な意味合いになります。
・告示第4条第2項
文言を読むだけだと若干意味が分かりにくいですが、特別講習の受講対象となった営業所において選任されている運行管理者全員が、特別講習受講通知のあった年度とその翌年度の2年連続で基礎講習か一般講習を受講しなければならない、というものになります。
・告示第5条
特別講習の規定です。第4条第2項を引用しているため、特別講習の受講発生=当該営業所の運行管理者全員が2年連続の講習受講義務発生という方程式が成り立つ形です。
①事故の場合
死者もしくは重傷者が発生した事故を引き起こした営業所における運行管理者となっており、ここでいう重傷者の定義は「自動車損害賠償保障法施行令第5条第2号又は第3号に該当する傷害」とされています。
この事故を引き起こした場合、事故報告の対象となりますが、その際の事故報告書の欄に「運行管理者」と「統括運行管理者」を記載することとなります。統括運行管理者はそのままの解釈(2名以上運行管理者が選任されている場合、統括運行管理者を1名決定する)ですが、ここでいう運行管理者は事故報告規則上「事故について最も責任のあると考えられる運行管理者」とされています(統括運行管理者との対比で、責任運行管理者と呼ばれることもあります)。
また、講習告示では、講習受講対象者として「事故等について相当の責任を有する者として運輸監理部長又は運輸支局長が指定した運行管理者」という表現がとられています。
実際の運用上は、「当該事故を引き起こした乗務員に対して出庫点呼を行った運行管理者」という扱いになっており、点呼実施者のケースによって、以下のとおり分岐します。
・統括運行管理者が点呼を行った場合は当該統括運行管理者のみが講習受講対象
・統括運行管理者以外の運行管理者(責任運行管理者)が点呼を行った場合は、統括運行管理者と責任運行管理者の2名が講習受講対象
・補助者が点呼を行った場合は、責任運行管理者がいないため、統括運行管理者のみが講習受講対象
②行政処分の場合
講習告示第5条において、「前条第2項各号に掲げる場合」とあり、第4条第2項第2号において、「道路運送法第40条の規定による処分(輸送の安全に係るものに限る。)の原因となった違反行為をした場合」が講習受講対象となっています。
また、解釈運用通達第48条の4(3)②において、「輸送の安全確保に係るものに違反をして行政処分を受ける営業所については、~中略~規則第48条各号の規定に対する違反について、相当の責任を有している~以下略~」と規定されています。
整理をすると、以下の要件が必要となります。
・事業者が道路運送法第40条における行政処分を受けた場合であること
※車両停止以上のものを行政処分といい、警告以下は行政処分ではないことから、50日車以下文書警告の場合は対象外であり、50日車を超えて実際に車両停止になった場合を指します。
・違反行為の中に、運輸規則第48条の運行管理者の業務に関する違反があり、その違反部分の中に、処分量定が10日車以上のものが含まれていること(警告は処分ではないため)
この場合に、統括運行管理者に対して特別講習の受講通知が発出されることとなります。
なお、事故で特別講習を受講済みの場合、その事故を端緒にして監査が実施され、行政処分による特別講習受講対象の要件を備えたとしても、原因は同じであることから、再度の受講は必要ないとされています。
行政処分を受けた営業所の『統括運行管理者』は、行政処分を受けた年度(当該年度に特別講習の開催がない場合には翌年度)に特別講習(2日間)を受講する他、行政処分を受けた年度及びその翌年度と連続して基礎講習もしくは一般講習を受講しなければなりません(行政処分を受けた時点で、当該年度内における基礎講習もしくは一般講習の開催がなくなってしまっている場合には、翌年度及び翌々年度に受講しなければなりません)。また、当該営業所の『統括以外の運行管理者』も、行政処分を受けた年度及びその翌年度と、連続して基礎講習もしくは一般講習を受講しなければなりません。当該基礎講習もしくは一般講習を受講してから2年度ごとに1回の受講に戻ります。そのため、受講年度が今までとずれてくるケースも発生しえます。
○運行管理者の講習については、以前は自動車事故対策機構(NASVA)が独占的に行っていたため、NASVAが運輸局から講習受講対象者の情報提供を受け、該当する管理者に対して受講をするよう通知を行っていたことがあります。しかし、平成24年度以降、講習認定機関制度が設けられ、NASVAを含め認定を受けた民間団体も実施出来るようになったため、今まで行っていた運行管理者講習の受講に関する通知が送られなくなりました。「運行管理者講習の受講通知が来ていないから受けなくてよいと思っていた」といって数年に渡って講習を受けていなかった、というケースが発生しないよう、事業者において受講すべき講習の種類や時期を間違えないように把握をしておいてください。
○なお、NASVAでは、運行管理者等指導講習の受講手帳を廃止し、修了証明書を発行する制度が始まっております。修了証明を今まで使っていた手帳に転記することはできませんので、手帳だけでなく修了証明書も適切に保管するようにしてください。詳しくはこちらをご参照ください。
○運行管理者講習の認定機関については、国交省のHPにて公表されております。
くわしくはこちらを参照ください(国交省のHPが開きます)
特別講習の認定を受けていない機関や、貨物や旅客の一方の業態でしか認定を受けていない機関がありますので、受講する際には種類を間違えないようにしてください。