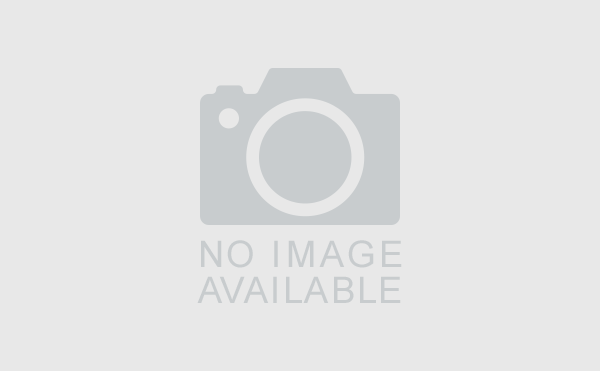令和7年5月14日付で手数料の取扱いに関するパブリックコメントの受付が開始されました。
概要はこちらのページを参照してください。
改正概要によりますと、貸切バス事業者に対して、安全コストの算出を行って報告を行う(おそらく運輸支局あて)ことを義務付けするようです。
以下補足説明
運賃と手数料の関係については別途記事を掲載したいと思っておりますが、大まかに説明すると、
「手数料を支払った後に残った額が、安全コストを下回っていた場合に、運送法第10条の割戻し違反となる」
という扱いは従前から行われているものとなります。
なお、手数料を差し引く前の運賃額自体が下限額を下回っている場合には、運送法第9条の2の違反(いわゆる下限割れ)となります。この場合には、安全コスト云々は関係なく、下限額に満たない額を収受している時点で違反となります。これに対し、運送法第10条は「手数料を含めた総額は下限額を超えているが、手数料を支払った結果、下限をした回った場合」というのが前提となり、そのうえで違反と認定されてしまうのが「安全コストを確保できていないほどに手数料を支払っている」場合ということになります。
運賃料金の下限額は、「安全コスト+安全コスト以外のコスト」を合算して算出されているものとなります。その「安全コスト」は絶対に確保しなければいけない額、ということになり、その安全コストを阻害するほどの手数料の支払いを行った場合に行政処分の対象となる、ということです。
ではその「安全コスト」とはどのくらいになるのか、といいますと、これについて事業経営状況は事業者ごとに千差万別なので、一律に額を出すことはできません。
今までは監査や巡回指導において、手数料を支払った額が下限額を下回っている場合に運輸局に通知を行い、運輸局がそれを第三者委員会に意見を求め、そこから調査を必要とした場合に初めて事業者に対して安全コストの算出を依頼する、ということが行われていました。
それをあらかじめ各事業者において安全コストを算出して報告を出していただくことになります。
現時点では、関東運輸局のHP(リンクはこちら)において、安全コストを算出したり、原価計算を行ったりするためのExcelファイルを公表しております。
また、本制度が施行される際には報告のための様式等が定められる可能性があります。その際には別途ご案内を行いたいと思います。